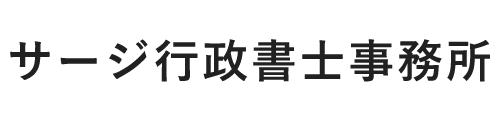大田区は、10月1日から11月21日まで「第3期SDGsおおたスカイパートナー」と「第2期SDGsおおたゴールドスカイパートナー」を募集します。大田区SDGs認定制度(SDGsおおたスカイパートナー/ゴールドスカイパートナー)の募集において、小規模事業者さま向けに“申請を進める手順とポイント”をご紹介します。
はじめに:なぜ今、SDGs認定なのか
大田区では、令和 7年10月1日から11月21日まで、「第3期 SDGsおおたスカイパートナー」および「第2期 SDGsおおたゴールドスカイパートナー」の募集を行っています。
この認定制度は、区内事業者がSDGs(持続可能な開発目標)に取り組むことを後押しし、地域全体で持続可能な社会づくりを推進することを目的としています。
小規模事業者にとって、SDGs認定を得ることは、ただ「設えとしてのラベル」を得るだけでなく、地元区や住民・他企業との連携・信頼強化、取引先へのアピール材料、行政支援制度の活用、さらには公共事業契約入札での加点、融資優遇といった具体的メリットも期待できます。
制度の仕組みを理解して、確実に申請して認定を得ることは、今後の事業展開上、有効な一歩となるでしょう。
認定制度の概要とメリット
認定制度の種類
制度には2段階あります。
①SDGsおおたスカイパートナー
区内でSDGsに取り組む企業・団体を認定。基本的な宣言・取組を行うもの。
②SDGsおおたゴールドスカイパートナー
より積極的な取組が条件。区との連携、脱炭素化や環境負荷低減の目標設定、進捗報告義務などが課せられます。
認定期間はいずれも 3年間。今回認定されれば、令和 8年1月1日〜令和10年12月31日が期間となります。
主なメリット・優遇措置
スカイパートナー・ゴールドとも共通するメリット、そしてゴールド認定限定の優遇制度があります。
共通メリット
・認定証の交付
・区のホームページ等で事業者名・取組内容等のPR掲載
・ゴールド認定特典
・区の「総合評価落札方式」(公共工事契約)で 加点 が得られる可能性
・区の中小企業融資あっせん制度「SDGs・脱炭素推進企業支援資金」の限度額拡大(1,000万円 → 2,000万円)
・きらぼし銀行の「SDGsおおたゴールドスカイパートナー応援ローン」で、1年目に所定金利より 0.1% 優遇
・区が運営する「公民連携SDGsプラットフォーム」との連携、イベント・情報発信機会
小規模事業者が認定申請を進めるステップ(7段階)
以下は、申請をスムーズに通すための手順と、注意すべきポイントです。
1、制度内容・募集要領を確認
大田区の募集ページや「申請の手引き」「記載例」を必ず入手して読み込む。提出書類の様式・フォーマットを正確に確認。
2、自社・事業のSDGs取組を整理 自社で実施済み・検討中の取組を、どの目標(17のゴール等)に結びつけるか整理。
特にゴールド認定を狙うなら、環境・CO₂排出量・省エネ・廃棄物削減など具体性を持たせた取組を用意。
3、必要書類を準備 スカイパートナー
1. 大田区SDGs認定制度申請書(第1号様式)
2. 宣言書(第2号様式)
ゴールドを狙う場合には加えて
3. 宣言書(第3号)
4. 認定要件チェックリスト(第4号様式)
申請時には「記載例」も参照してください。
4宣言書・要件チェックリストの内容精査
宣言文は “このようにSDGsに貢献します” と事業者としての意志を明記。ゴールド要件チェックリストは、全ての必須項目をクリアできるように準備(特に CO₂排出量可視化などの要素)
5申請フォーム送信
様式が揃ったら、区指定の申請フォーム(Web)から送信。書類を添付する。
6、審査・認定
区側で審査が行われ、認定可否が判断されます。欠陥や補正事項があれば補正要求が来る可能性。
7、認定後の対応
認定証の受領、区HP等への掲載、取組の公開・PR、(ゴールドの場合)進捗報告義務が年度ごとに発生。
また、認定期間内に事業者名・代表者等の変更があれば変更届出をする必要があります。
行政書士から見る、申請を“通りやすくする”ためのコツ
取組内容の具体性を持たせる
たとえば「資源を節約します」ではなく、「LED照明への切替」「古紙リサイクル率向上」「包装材の再利用化率向上」など、数値や工程を入れると説得力が増します。
CO₂排出量の可視化を早めに準備
ゴールド認定要件には、チェックリスト項目の一つに「温室効果ガスの排出量測定」が含まれており、CO₂排出量可視化サービスの導入支援も制度上明記されています。早めに検討・導入しておくとよいでしょう。
整合性と整頓性を重視
複数書類で矛盾しないように。宣言書、要件チェックリスト、申請書における表現・数値は一貫性を保持するようチェック。
補正対応を速やかに行う
審査時に補正を求められた場合、速やか・的確に対応すること。
認定後フォローを念頭に置く
ゴールド認定では毎年度の進捗報告が必要なので、取組実績を日常的に記録しておくこと。また、認定取得をPRに使えるよう、HP・パンフレットへの記載準備もしておくとよいでしょう。
小規模事業者にとっての取り組みテーマ例(参考案)
省エネ・照明設備の更新(LED・センサー照明化)
再生可能エネルギー導入(太陽光パネル設置、小規模蓄電池導入)
廃棄物削減・リサイクル率向上
グリーン調達(環境配慮型資材の採用)
フードロス削減(飲食業・食品関連事業者向け)
働き方改革・多様性(女性活躍、高齢者雇用、障がい者雇用など)
地域との連携・環境教育・地域貢献活動
こうしたテーマは、SDGsの各目標(例:12「つくる責任つかう責任」、13「気候変動対策」、8「働きがいも産業も」など)につなげて表現できます。
おわりに:早めの準備と戦略性が成功のポイント
この募集期間(10月1日〜11月21日)内に申請を完了させることが前提ですが、実際には準備期間を余裕を持って確保することをおすすめします。特に、ゴールド認定を目指す場合には、CO₂測定体制や取組の裏付けデータを整備しておく必要があります。
サージ行政書士事務所は書類作成支援・記載内容のブラッシュアップ・補正対応支援などを通じて、皆さまが確実に認定を得られるようサポートいたします。ご希望であれば、申請支援プランもご案内できますので、お気軽にご相談ください。